そうか、「クラの神話」のことだったか。
クラの神話
ギリガンとキテイのところまで読みました。 そして気づいた。
ヨナスの後だからですかね、ハイデガーを連想していたから「クラの神話」を思い出したのでしょう。 ローマ神話の女神クラ(Cura)が泥人形から「人間」を作り出す話。
彼女は一人で「人間」を作ることができなくて、いろいろな神々の助けを借りる。 すると、それぞれの神が「人間の所有権は私にある」と主張し、大混乱が起きた。 困ったクラが偉い神様にお伺いを立てたところ「人間が死んだら、その身体は大地の神に、その精神は天空の神に返しなさい。生きている間は、あなたが面倒を見るのです」とおっしゃられた。 それで人間は生きている間「気苦労 cura」が耐えないというお話です。
これが「誰に責任があるか」の責任論だったわけですね。 そしてCuraは英語のcureやcare, curiosity の語源だから「ケアの倫理」でもある。 ハイデガーは「気遣い」という概念を分析し、そこから「情態性への了解」という要素を取り出します。
これが精神科医ヤスパースの Verstehen となり、心理学で「共感的理解」と呼ばれるようになる。 だから「ケア」と「共感」が密接に結びついています。
これは「クラの神話」に由来するわけだ。
ケアの原理
と同時に、ドイツ系の哲学とアメリカ系との差異も感じました。
ヨナスはユダヤ人なので、師匠であるハイデガーを愛しながら、でも憎んでいます。 アンビバレントな感情から「クラの神話」を読んでいる。 なんとか師匠の「気遣い」という概念を生かしながら、どうすればナチス的にならずに済むか。 その解毒化を考えてますね。 人はクラのように無力で、誰かを頼ってでないと何も成し遂げられない。
それに対しアメリカの哲学はハイデガーを無視したい。 裏で参考にしても表には出さない。 やはり「ドイツは敵国」だからでしょう。 ハイデガーを引用すると各界からバッシングを受けるので忌避している。
無視している分、ハイデガーの影響がもろに出てしまう。 「ケア」の話が「女性原理」みたいに語られます。 「女神クラの原理」ですからね。 「ケアは女性の仕事」という先入観が隠れている。 フェミニズムの支えになっていますが、ちょっと怖いですね。
たとえば、自閉症研究のバロン=コーエンが最近出した『パターン・シーカー』にもあって、「男性脳=システム指向 vs 女性脳=共感指向」という図式が顕著かな。 自閉症の特性を「パターンを見つけ出す能力」に見て、それが人類の発展に貢献してきた。 それはそうだろうなあ、と思います。 必要があって自閉傾向があるのだろうから。
でも、その特性を男性の傾向と見て、その原因を「脳」に落とし込む。 これをされると「共感は女性に任せるほうがいい」という論が出てくるじゃないですか。 ケアが女性に押し付けられてきたことが問題だったのに、話が反転してしまう。
もちろん「ケアの責任」は男性にも生じます。 何か誤魔化して逃げてますね。 たぶん「ケア」の話になると「育児」に繋がりやすいからかな。 でも現代社会では「介護」も「ケア」の分野です。 介護を「女性の仕事」と限定すれば社会が破綻する。 ヨナスもそう。 「未来への責任」を重視すると、老人や病人が射程から外れてしまう。
そもそも「自己責任」が難しくなるのは病気に罹ったり年老いたりしたときです。 それは人生について回る問題だから、お釈迦さんも「生老病死」と取り上げたわけで。
一度病気になれば、どれほど自立した人でも「人に頼る」という事態が生まれます。 その場に「責任」が生じる。 瀕死の状態で、もう「未来」がないとして、そのとき、周りの人間は何ができるか。 それが「責任」にまつわる基本問題です。
今のところ戸谷先生の本では扱われていません。 というか、ほかの人もか。 「ケア」や「共感」に関する議論がすぐ「子ども」に向かうことに違和感を感じます。
まとめ
それなら「介護」を論じている本を読めばいいわけだな。 哲学で「介護」と向き合ってるのは誰だろう? 青臭い「死」ではなく、うんこ臭い「老いの介護」について。
おっと、古今の哲学者たちが「若造」のように思えてきた。
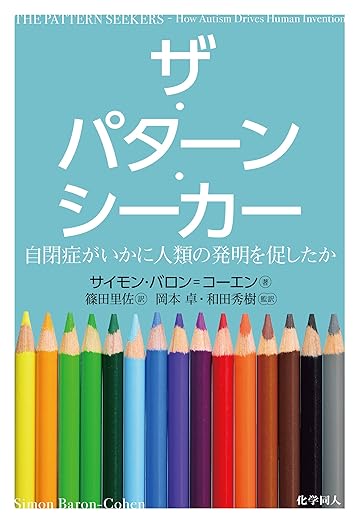 ザ・パターン・シーカー: 自閉症がいかに人類の発明を促したか
ザ・パターン・シーカー: 自閉症がいかに人類の発明を促したか