夕暮れは老人に厳しい。 急に本が読めなくなるのである。 目玉の奥の方がズキズキ痛くなる。 仕方ないので夜は軽いエッセイか対談集を読むようになりました。
六人の橋本治
久々に読みながら感動した対談集。 橋本治は源氏物語や平家物語の現代語版を手がけてきました。 その新刊時に開かれるイベントでしょうか。 橋本治が6人の著名人と対談しています。 あと、おまけでもう一つ対談が入っている。
このどれも同じ構造なのがすごいですね。 対談者は「私は橋本治を知っている」と自負している。 それに対し橋本治は「オレはオレがわからない」のスタンスです。 「ここは書けたがここは書けなかった」を自覚している。 なぜ書けなかったのかを自己分析し、その分析でも割り切れないものが残ると課題の洗い出しをする。 その話に付き合ううちに対談者の方も「私もわからなくなった」と戸惑いを感じる。 中には「いや、私は知っている」と固執する人もいるけど、破綻していく。
まるでソクラテスなんですよね。 これが「不知の自覚」ということか。 それが平明な日本語で行われていることに打ち震えてしまう。 やっぱりすごいや、橋本治。
表面的に読んでも面白いです。 日本の小説がどういう歴史なのか、美術史はどう読めばいいのか。 源氏物語はどの順に書かれたか、平家物語の婚姻関係は誰の欲望か。 何が常識とされてきて、何が橋本治を苛立たせるのか。 そこを逐一言語化していく。
なので対談者側の「私は知っている」という既知が揺らぎます。 もう一度足元を見つめ直し「自分とは何か」が問われる。 橋本治の関心はどうやら「小林秀雄が指し示した『あっち』」らしいと見えてきます。 この「あっち」ですね。
日本は明治に入り、急速に西洋文化を吸収することで、まるで初めから「西洋諸国の一員」であったかのような顔をしている。 そこが気に食わない。 西洋文化を吸収するとき、それに足る土壌がすでにあったから、近代化が進められたのだろう。 今の日本は近代化の行き詰まりにある。 ヨーロッパもアメリカも、一昔みたいな「幸せのモデル」とはならない。 そこを目指しても地獄に落ちるのは目に見えている。
じゃあ、その土壌とは何か。 現代の日本は、近代以前に戻り「日本の進む道」を立て直す時期にあるんじゃないだろうか。 そこが橋本治の問題意識です。
そして、その「あっち」がなかなか見えない。
小林秀雄の恵み
面白そうじゃないですか。 でも源氏物語や平家物語は長いからなあ。 挙がっている著書の中でササッと読めそうなのは「小林秀雄」か。 ということで「小林秀雄の恵み」に取り掛かりました。
はい、ビンゴ。 これこそまさに「オレはオレのことがわからない」でした。 「橋本治は橋本治がわからない」だし「小林秀雄は小林秀雄がわからない」。 小林秀雄の『本居宣長』を橋本治が読み、その不可解さを解明していきます。
みんなは「小林秀雄」をわかっている。 国語の教科書に載って「このときの作者の気持ちを述べなさい」と出題されたりする。 誰もが「既知」と思っている評論家です。 その「小林秀雄」を小林秀雄は嫌っていたのだろう。 誰がわかるもんか、オレでさえわからないのに。 そういう思いが『本居宣長』には溢れてます。
こうした小林秀雄を橋本治は「いいやつだ」と直観します。 「不知」を実感している同類だからでしょうか。 「既知」にあぐらをかく契沖や真淵は「いやなやつ」です。 橋本治の判断基準はわかりやすい。 小林秀雄は「いいやつ」だから助けてやりたい。 その泥舟に乗って、一緒に沼地に沈んでいきたい。
「小林秀雄の恵み」は読みやすい本です。 これ一冊で小林秀雄と出会える。 さらに本居宣長とも出会えます。 そして大盤振る舞いで『源氏物語』の紫式部までも見えてくる。 みんな「いいやつ」です。 日本の「近代」を準備した作家たちです。
たとえば『源氏物語』に出てくる和歌について。 地の文はダメなんですよ、敬語文化だから。 日本語は敬語に覆われていて、人はただの「肩書き」に過ぎない。 システムを構成する駒であり、生きていません。 そこを現代語訳しても「個人」は出てこない。
でも和歌は違います。 和歌は敬語を拒絶します。 自分の心と向き合う「生の声」が映し出される。 「個人」として生きているのが和歌であり、紫式部はそれを自覚しながら物語を綴っている。 日本の土壌にあるのはこの「生の声」です。
これを発見した橋本治はすごい。
それを書き表すには和歌も現代語にしないといけない。 従来の『源氏物語』は和歌のところだけ和歌のままなんです。 それだと読者は読み飛ばしてしまいます。 「個人」が描かれていると気づかないまま「古文って苦手なのよね」と地の文だけ読んでしまう。 すると『源氏物語』はつまらないハーレークインになってしまう。
日本の文化に「個人」を活かす表現法があった。 その事実がこれまで「近代」を支え、もしかすると現代を乗り越える「未来」の礎になるかもしれない。 小林秀雄はそれに気づいて、なんとかその原理を読み解こうと苦闘している。
ほんと「いいやつ」なんですよ。
まとめ
以上のまとめにはウソが入ってます。
というのは橋本治はそのあとも『本居宣長』を再読、再々読と何度も読み直し、そのたびに新しい視点を持って帰ってくるからです。 読者としての橋本治。 そのパフォーマンスがこの本の見どころになっている。 「読む」とはそういうことなのかって感動します。
 対談集-六人の橋本治 (中公文庫 は 31-42) 文庫 – 2024/5/22
対談集-六人の橋本治 (中公文庫 は 31-42) 文庫 – 2024/5/22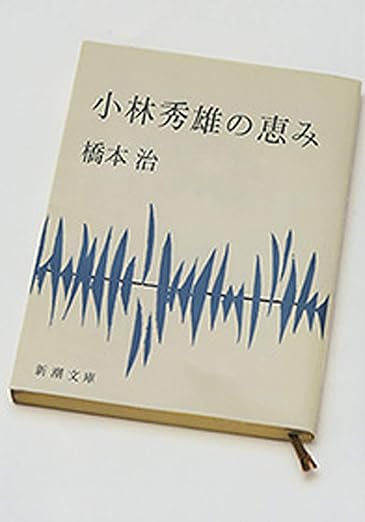 小林秀雄の恵み(新潮文庫) Kindle版
小林秀雄の恵み(新潮文庫) Kindle版