科学とは何か
半分くらいまで読みました。 「IMRAD」が何度も出てくるのでまとめてみます。
IMRADは科学論文の書き方としてアメリカで1940年代に現れ、 1970年頃にメインストリームとなりました。 たしかに大学で習った覚えがある。 でも当時はまだ「真新しい作法」であったわけか。 ちょっと意外です。
- 序文:Introduction
- 対象と方法:Material & Method
- 結果:Result
- 考察:Discussion
この4項目でレポートを書く。 学術雑誌に投稿するときの形式ですね。 頭文字を並べてIMRAD。 「Aがないじゃないか」と思うけどAndのAだろうか。
小熊先生は書いてないけど、 この形式は「軍用目的」と考えると捉えやすい。 1940年代は「戦時中」です。 「その道30年の達人のみがこの結果になります」ではダメ。 徴兵されたばかりの20代でも扱える報告書の書式。 だから結果がわかりやすい。 結果に至るための手続きもわかりやすい。
そのためIMRADはクックパッドのレシピのようになっています。 材料があって手順があって、誰がやっても美味しくなる。 誰がやっても同じ結果となる「再現性」を重視しています。 「それが科学だ」という思想がありますね。
- 序文:レシピの紹介文
- 対象と方法:材料と作り方
- 結果:完成写真
- 考察:コツ、ポイント
これがレポートの基本形。
前回「5パラグラフ・エッセイには how がない」と書きましたが、 このIMRADはむしろ how を重視しています。 科学論文とは「ハウ・ツー」だからです。 追試できるように情報開示する。
小熊先生は「魔法と科学の違い」を次のように述べています。
魔法はプロセスを公開しません。魔法では、プロセスを秘密にし、 結果だけ見せて「すごい」と思わせます。 それに対し科学は公開が原則で、 誰でも疑っていいし、お互いに批判や対話をしながら進歩できます。
反論されると顔を真っ赤にして怒り出すのは「科学」ではありません。
人文科学への応用
そしてIMRADは他の分野でも採用されます。
ただし人文科学には「先行研究の検討」が入ってくる。 それで5パラグラフ・エッセイを混合した形式に発展しました。 小熊先生は「実験/調査型・資料分析型・理論型・複合型」 の4分類を紹介していますが、どれも下記パターンを踏襲しています。
- 序論:序文(主題)。仮説を立てる。
- 本論1:先行研究の検討。この仮説の何が新しいか。
- 本論2:対象と方法。誰もが追試できるようにする。
- 本論3:結果。仮説を検証する。
- 結論:考察。全体をまとめる。
それぞれのパラグラフは研究のタイプによって伸縮が起こります。 先行研究の検討を序論で軽く済ませることもある。 反対に先行研究が長くなって、対象や方法もそこに含まれてしまう。 あるいは結果までは短く、考察が論文の大半を占める。 そういう場合も起こります。
これは「文系の論文だからそうなる」ということではありません。 そもそも「理系か文系か」は日本でしか通用しません。 これは「教科書が横書きか縦書きか」の違いでしかないのですから。 (あ、中国や韓国ではどうなんだろう?)
自然科学と人文科学を分けたのはディルタイだったかな。 ヴィンデルバントは「法則定立的」と「個性記述的」に分類しました。
- 自然科学:法則定立的。いつでもどこでも通用する普遍性を探す。
- 人文科学:個性記述的。そのときそこで起こった個別性を明らかにする。
自然科学は物理学や化学で「いつでもどこでも」同じ結果が得られます。 人文科学は歴史学や地理学なので「そのときそこで」の事実を知ろうとします。 普遍か個別かの「テーマの違い」がある。
ここあたり難しいなあ。
主題と対象
というのも人文科学では「主題と対象」の混同が起こりやすいからです。 小熊先生も一章を費やしてそこを論じています。 それくらい難しい。
クックパッドで言えば主題とは「秋を味わおう」です。 抽象的です。 これだけでは何を言っているかわからない。
そこで対象として「サンマの炭火焼き」を扱う。 具体的な事物のレベルに落とします。 これが自然科学の論文ならやりやすい。
自然科学が扱うのは法則性です。 万有引力の法則とかです。 これは目に見えないし、耳にも聞こえない。 感覚で捉えることはできません。
そこで鉄と石をピサの斜塔から落としてみる。 鉄や石という具体的な「対象」を使って実験してみる。 「鉄のほうが重いから先に落ちるだろうか」と仮説を立てて。 誰もが再現できる方法を使って仮説を検証する。
自然科学は「法則を探す」なので、主題と対象を区別がしやすい。 でも人文科学は「個性記述」なので対象が主題と重なっている。 「アイヌの熊送りについて」だと、その儀式の様子を記述するだけで 一つの論文が出来上がるし、資料としても価値がある。
でも「アイヌの人たちの霊魂観」を主題にして、 それを明らかにするために「熊送り儀式」を対象とすることもあるなあ。 その場合は「主題と対象」は明確に分かれる。 こうなった場合が人文科学の「論文」なのかもしれない。 個性記述的だし。
とすると「熊送り」を記述しただけだと「一次資料」ということになるだろうか。
まとめ
資料と論文を分けて考える。 もちろん「資料」が論文として掲載されてもいいんですけどね。 「新たに発掘された土器にこんなのがあった」というのも発見だし。
でもそこから「従来とは異なる稲作伝播のルートがあるんじゃないか」 と仮説が生まれれば「論文」。 そう分類すると人文科学の論文をレシピとして記述できそうですね。
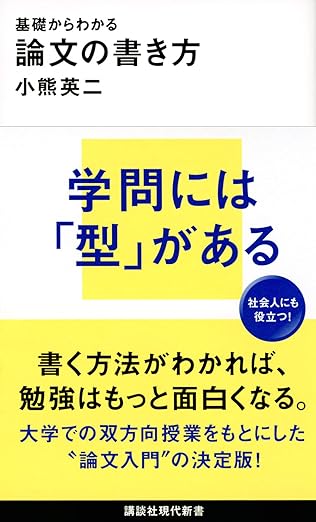 基礎からわかる 論文の書き方 (講談社現代新書)
基礎からわかる 論文の書き方 (講談社現代新書)