太い本でまだ3分の一ほど読んだとこだけど、 これはまずい。
カウンセリングとは何か
東畑先生の創作神話。 歴史修正主義みたいなものかな。 自分自身を第4世代に位置づけている。 この時代の使命を自己定義し答えようとしています。
第1世代はロジャーズのカウンセリングで、 第2世代は専門家のための原論が作られた時代。 第3世代になって流派ごとの各論が乱立し、 第4世代は再び原論を作り出すことを求められている。
でもそんな「世代」が臨床心理学にあっただろうか。 第1世代は心理検査に明け暮れカウンセリングなんてしてないし、 第2世代の原論もほとんどが精神科医によって整備され 心理学者はそれを借用したに過ぎない。 自前では何も作ってないでしょう。
薬物療法の興隆で、精神療法を専門にしていた先生方が 文系のポストに流れ込んできたのが第2世代。 日本の風土で培われた面接技法のノウハウが臨床心理学に託された。 この膨大な遺産を守ることが何よりも優先事項でした。
それに対し、本来心理学で担うべきカウンセリングについて 海外の「原論」が輸入されたのが第3世代です。 決して各論ではない。
それは心理士の国家資格化に伴い、欧米の水準に追いつく試みだった。 精神分析は医師免許がないと行えないのだから 心理学者が語っていいアプローチではない。 心理士のカウンセリングにも効果があることを検証し、 エヴィデンスに重点が置かれた。
その上での第4世代でしょうね。 結局これまで資格問題に右往左往して、 ユーザー目線に立つことを怠ってきた。 でも一応国家資格は出来上がったことだし、 これからは自分たちのサービスを広く知ってもらう段階だろう。 そこでユーザー向けの「神話」が必要となる。 内々の符牒を転がしてる場合じゃない。
東畑先生の認識はズレてるけど、ここぞの勝負勘は冴えていると思います。
教育学の二の舞か
でもなぜ、このような本が民間から出てくるのかと思う。 一般の人たちにアクセスしやすい道筋を作るのは大学の使命じゃないか。
とすると、教育学と同じことが臨床心理学でも起こっているのかもしれない。 資格制度ができたことでカリキュラムをこなすことに日々が追われ 「そもそも教育とは何か」や「教えるとはいかなることか」といった問いが なおざりにされている。 各教科ごとに分裂し、教授方法だけ研究される事態に陥っている。
同じようなことが臨床心理学にもあって、 それが「各論の乱立」と目に映ったのかもしれない。 方法論はあるけど「そもそも論」がない。
でも、ない訳じゃない。 教育学原論も大学で教えているけど人気がないんです。 直接役に立たないから。 どんな議論がされてるにせよ、すでに「学校」がある。 ユーザーが「学校」に来ている。 ノイラートの舟なので、一から問い直すのが難しい。
カウンセリングは幸い、まだ「義務教育」になってません。 出航してない。 「舟」の設計を模索する時間があります。 どんな人に乗ってもらって、どんな体験をしてほしいか。 夢を語ることができる。
次世代の危惧
これ、ちゃんとやっとかないとダメでしょうね。 エヴィデンスを詰めていって 万能なカウンセリング理論を構築したら、 それは生成AIに乗っ取られるということだから。
すでに生成AIは相談業務に入り込んできて 「相談依存」が問題になりつつある。 カウンセリング原論が必要なのはこうした現代的状況も関係がある。
教育のほうはもう生成AIの侵略が始まっています。 GIGA構想で教育をデジタル化し、 個々の児童に合わせた教材を提供するほうが、 従来の一斉教育よりも細やかな対応ができる。 不登校になっても学力が保証される。 教師による盗撮問題も起こりません。
でも、デジタル化することで教育は大切な何かを失います。 これは「そもそも論」がなかったら言語化できない。 そうしたシロモノです。 教育学原論に予算を回してくれないと 「教科書の問題に答えることだけしかできない子どもたち」を量産してしまう。 だって、それに最適化するのだから。 これでは誰も幸せにしません。
まとめ
キーワードは「他者」だと思うし、とくにカウンセリングは 「一人だと堂々巡りになるのに、他者に話すと物語が進むのはなぜ?」だろう。
でも東畑先生をしてもまだ「他者」が薄い。 心が環境と身体に挟まれた「個人の中」になっています。 その図式は古すぎるし、生成AIの介入を許してしまう。
危うい。
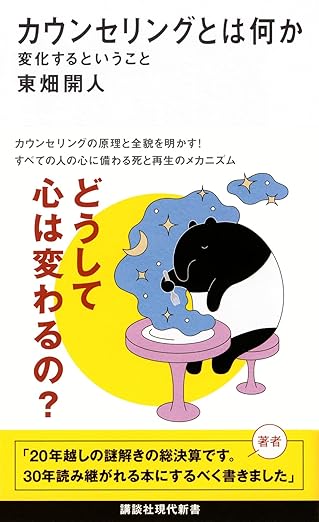 カウンセリングとは何か 変化するということ (講談社現代新書 2787)
カウンセリングとは何か 変化するということ (講談社現代新書 2787)