読みやすかったし勉強になりました。
メインは水谷さん?
これは漫画家の水谷緑さんがフィンランドでオープンダイアローグの見学をし、日本でも行われてないか取材したら、まだ斎藤先生と森川先生くらいしかいなかった、という話かな。 斎藤先生が前面に出てるけど、なんとなく「頼まれてQ&Aを寄稿しました」というスタンスだし。 斎藤先生が自分の過去話をするとは珍しい。
水谷さんは医療関係のマンガをよく描いている人で、ドラマ化された作品もあります。 ただテレビはほとんど見ないので申し訳ない。 どんな作品なのかは知りません。
わからないけど、たぶんその取材の途中で「オープンダイアローグ」と出会ったんじゃないでしょうか。 それで本場フィンランドまで研修に行ってきた。 普通はそこまで行動しないので、なにか事情はあるんだろうけどわからない。 わからないけど、その研修が自分自身にとってサウナのように心地よかった。 それはわかります。
フィンランドのオープンダイアローグは「傾聴と自己開示」ですね。 相槌を打たない。 共感もしない。 一見とても冷たいけれど、セラピスト側の真剣さが伝わってくる。 対立を恐れないというか、葛藤のあることを当たり前と受け入れ、それを直接患者さんにぶつけるのではなく、スタッフ間の話し合いで開示する。
開示するけど、解決はしない。 「いろいろあるものだ」を「お盆の上に置いていくように」並べていく。 その中で使えそうなのを患者さんに選んでもらうスタンスです。
日本式はどうか
ところが、日本に戻って取材すると、この雰囲気じゃないみたいですね。 「共感」が先立って「なんとかしなきゃ」の焦りを感じます。 しかも日本人は相槌を打つ。 スタッフ間の話し合いも、お互いの立場を慮っていて「葛藤」として熟成していない。
でもそうした実践を続けるうちに「何もしなくても何とかなるものだ」の感覚が掴めてくる。 中動態的なゆるさが生まれてくる。 だんだん力が抜けて、やっと日本でどう応用していくか見えてきたところみたい。
本場の「いつでもすぐに」はまだ日本では難しい。 「2週間後にまた会いましょう」と間隔が空いてしまうようです。 1時間半のセッションも、日本ではちょっと長すぎて1時間がいいかもしれない。 「今日は話すことがありません」と言われたら、それは回復の兆候だから、早めに切り上げてもいい。
そうした力加減を模索している段階なのだと思いました。
無力感の共有
マンガで実践例がいくつか上がってますが、いずれも重めの統合失調症のケースです。 それが「対話」を通して変化していく。
患者さんの苦しさや家族の焦りがうまく表現されている。 これは水谷さんの力量だなあ。 治療者側の無力感もちゃんと出ていて、でも何とかなるわけですよ。 薬も入院もなく。 ほんとにこんなにうまくいくものだろうか。
それぞれのケースを見て思うのは「無力感の共有」なのかな。 患者さんの中にどうしようもない「この世への無力感」があり、それが家族に伝染している。 言葉にならない無力感を表現しようとすると、はじめは「幻聴や妄想」に見えるのでしょう。
でもチームで「無力感」を共有すると、チームの中での「対話」に変わる。 「症状」で表現する必要がなくなり、少し気持ちが軽くなる。 気持ちが軽くなると「無力感」を背負う勇気が出てくるようです。
ここあたり水谷さんが的確に捉えていて転移には「愛されたい」と「わかってほしい」の2つがあるんですよね。 ビオンだとLリンクとKリンク。 この2種類がある。 「こんなこと言うと嫌われるんじゃないか。でもわかって欲しいし」と葛藤している。 この「わかってほしい」が働くときオープンダイアローグが機能するんだなと感じました。
人間って強いなあ。 「無力感を背負う」なんて生半可なことじゃないよ。 でもそれをしている人たちがいるんだなあ。 すごい。
まとめ
「書くこと」に「対話」が応用できるか、が読んでいるときの関心でしたが、「やっぱり一人じゃ無理だな」が感想です。 誰か自分の話を聞いてくれる人がいないと「書くこと」は一人で背負えないのかもしれない。
大学だと、ほら、講義という形式で「他の人たちに聞いてもらう」ができるじゃないですか。 あれが自分の助けになっているんだろうなあ。 それも広義の「オープンダイアローグ」になっている。
大学人でない場合は、その代用となる「ダイアローグ」をどう作るか。
追記
あ、そっか。 2つめのケースが水谷さん自身の相談だったか。
それを森川先生のところでオープンダイアローグしてもらって「あれ?」となったわけね。 それからフィンランドに行ったんだろうか??
そうじゃないと、森川先生に解説を書いてもらわないのは変だものなあ。
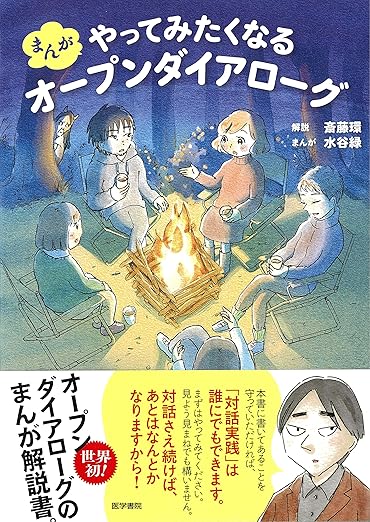 まんが やってみたくなるオープンダイアローグ
まんが やってみたくなるオープンダイアローグ