注:『中論』のテトラレンマ(四句分別)とは関係ありません。
読み手に届く文章技術
第4章の「根拠」のところ。 伝達文とか物語文とか分類していて参考になりました。
この分類、意見文を説明するための下ごしらえですね。 自分の意見を言語化するとき、 どうすれば読み手に自分の主張が伝わるか。 それをスキルとして考察しています。
まず考察の対象はオープンクエスチョンの形を取る。 なぜ?どのように?それは何か? 5W1Hの形式で問いが立てられる。 でも、そのまま扱ってはいけない、と。
なるほどなあ。 オープンをオープンのまま考えていくと綱渡りになります。 迷路を迷路のまま記述するというか。 読んでも頭に入ってこない「哲学書」になってしまう。
それで一旦クローズドクエスチョンに読み替えます。 たとえば「生成AIは人間の仕事を奪うだろうか」とか 「思い出を残すには写真がいいかビデオがいいか」とか。 クローズドにすると焦点が絞りやすい。
クローズドにすると文章はディベートになります。 「仕事を奪う/奪わない」という二項対立になる。 こうすると読者は議論について行きやすい。 それぞれの立場の論拠を見ながら 「どちらがいいか」と考えていける。
ただし、意見文自体はディベートではありません。 石黒先生としては、もとのテーマを深めるための方便です。 結論として「奪うとも言えるし、奪わないとも言える」のような 総合的な視点が落とし所になります。 そうなって初めて「意見」と言える。
テトラレンマ
この考察を引き継ぐと、文章には4パターンあることになります。
- それはAである
- それはAなのか、Bなのか
- それはAでもあり、Bでもある
- それはAでもなく、Bでもない
この4つがある。
それぞれに従って、文章を分類し直すと:
- 伝達文はパターン1である
- 議論文はパターン2である
- 意見文はパターン3である
- 考察文はパターン4である
上記のようになります。 勝手に名付けてみました。
石黒先生が分類する「伝達文・説明文・物語文」はいずれも「それはAである」の形式を取ります。 情報を伝えるのが目的だから、そこに葛藤は含まれません。
伝達文自体はニュースのようなものです。 「これこれ、こういうことがありました」と事実が陳述される。 伝達するのが手続きや方法の場合は説明文になります。 パソコンとかのマニュアルですね。 それに対し、個人の体験を伝達するのが物語文。
なのでこの3つは大枠ではパターン1になります。 第1章から第3章までの「差分・構成・視点」はそれぞれ、 伝達文・説明文・物語文の要所を示していると言えるでしょう。 「それはAである」の伝え方が書かれている。
意見文
第4章からは意見文の話になります。
意見文は「なぜそう言えるか」を示しながら、 読者を説得しなければなりません。 そこで重要になるのが「根拠・定義・引用」で、 その話が第6章まで続きます。
石黒先生の分類では「意見文」だけですが、 ここは「議論文」と「意見文」に分けて良かったんじゃないかと思う。 というのも「根拠・定義・引用」は 「AかBか」を論じるためのものであって 「議論」の話をしているからです。
そして石黒先生自身、それだけでは「意見」でないと考えている。 「AかBか。私はAだと思う」では「意見」になりません。 葛藤を描きながら、その葛藤を俯瞰的に見る視点が必要になります。 この葛藤はどうなっているのか、と。
これも「鳥の目」かな。 場合分けや時間を導入する。 「あるときはAであり、あるときはBである」と分析していく。 葛藤を葛藤のままに受け止め、それを乗り越えていく。 そうなって初めて上質の「意見」となります。 これはパターン3の形をしている。
ではどうやって俯瞰的な視点を確保するか。
それが「読者目線」ですね。 第7章から「推敲・設計・配慮」に注目し 「読者目線とは何か」に移っていく。 本書の構成はそうなっています。
ただ「読者」に力点が移っていくのだけど 「生成AI・SNS・電子メール」というツールの話も絡めるため、 残念なことに焦点がぼやけてしまった。 そういう印象です。
第4章で「Aでもあり、Bでもある」の話を出したので 「意見文についてはすでに書いてるし」になっちゃったのでしょう。 「読者目線」を掘り下げるはずが 「web時代の敬語の使い方」みたいな文章読本になってます。 これは惜しい。
パターン4
第10章の「総合」は石黒先生自身の「文章技術」を解説していて、 ここから読むのがいいかもしれません。 というのも、まさにパターン4が描かれているからです。
話は「コビトカバ」や「メクラネズミ」のように、 差別語が含まれる動物名から始まります。 これを改名すべきか、それとも残すべきか。 パターン2の「Aであるか、Bであるか」に話をパラフレーズします。 ここはクローズドの部分。
そこから差別語を巡る言説を外観し、全体像を捉える。 でもそれは「どちらにも理があります」といった無難な結論に落とすためではない。 もう一歩、歩みを進め「いま何が起きているのか」を浮き彫りにするためである。 石黒先生は「言語衛生」という概念を導き出し、 こうした葛藤自体を排除しようとする姿勢を問題視します。
喩えてみると、これはゲシュタルトの「地」に当たります。 葛藤として浮き上がってきたものを「図」とした場合、 何が「地」にあるのか。 そこを取り出すのがパターン4であり、本当の意味での「考察」です。
振り返ると、第4章でそのことは書かれていました。 オープンクエスチョンを一旦クローズドに読み替える。 「一旦読み替える」とは 「最後はオープンに戻ること」です。 「そもそも差別とは何か」といった、答えのない問いを引き受ける。
哲学対話が思い浮かびます。 哲学対話はディベートではありません。 葛藤が浮き彫りになったとき、そこにいる誰かが 「そもそも〜とは何だろう?」とつぶやく。 「図」から「地」にフォーカスが移る。 その場のみんなが「おおっ」とどよめくことです。
ネガティブ・ケイパビリティもこれでしょう。 葛藤に耐えて我慢することではない。 葛藤から浮き上がる「地」に目を凝らす。 そこがパターン4に当たります。
まとめ
あと石黒先生の「考える・調べる・書く」の相互作用も良かった。 清水先生の図式なら「考える→・←調べる→・←書く」となりそうで、 この「・」を考えるのも面白そう。
考えるから調べるのだし、調べるから考えも深まる。 それぞれが単体では成立しない。 さてそのとき「・」には何があるのか。
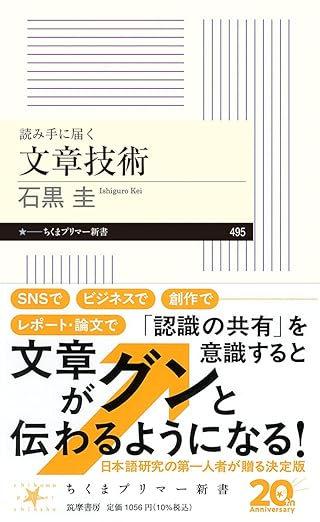 読み手に届く 文章技術 (ちくまプリマー新書 495)
読み手に届く 文章技術 (ちくまプリマー新書 495)